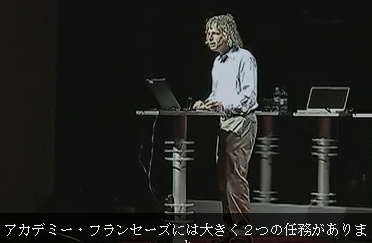著書である『思考する言語』の特別の予告として、「暴力にまつわる社会的通念」について語ったスティーブン・ピンカーが、言語と言語がどのように人の心を表現するのか、また私たちが選ぶ言葉がどれほど意図を伝達するのかを解説します。
話される言葉とそこに意図を隠す方法を上手く使えば、人間関係を円滑に、そして優位に展開することができるかもしれません。
言語はそれが意味するものを明確に定義するために、これまでに何度も用法を制定されてきましたが、それはイタチごっこのように次から次へと新しい言葉や意味が増えていきます。こういった言語の性質は、人間の性質からくるものだとスティーブン・ピンカーは指摘します。
まず、言語を定義付けることによって誰にでも理解可能なものとし、世界を概念化するための認知的機構としての役割を与えました。そして、言語に抽象性を与えることで、矛盾した2つの問題を解決することができるようになりました。「曖昧さ」というこの性質は、言語が”不完全”や”欠陥”ではなく、人間関係を円滑に進めるために生み出された人間的なものだといいます。
つまり、”言語はどのように世界を概念化するのか”、また、”どのようにお互いに関わるのか”という人間の性質を反映した総体的な創造物だということがいえます。言語のあいまい性と複雑性を分析することで、何が私たちを動かしているのかを見る窓を獲得することができます。